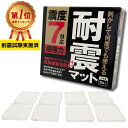ペットのための地震対策 日頃の備えと地震発生時の対応〜鳥・魚・爬虫類編〜

日本は地震大国です。毎年のように日本各地で地震があり、近い将来にさらに大規模な地震が起こることが予測されています。
地震への不安は誰しも感じていることですが、動物を飼っている人にはさら不安に思われているでしょう。中でも犬・猫以外のペットについては、情報集めに苦労されている方もいるかもしれません。
いざというときのため、鳥・魚・爬虫類の地震対策についての情報をまとめました。
ペットがいる家の防災対策の基本
ペットがいる・いないに関わらず、家の中の安全対策は防災の基本です。
家具の固定方法や中身の飛び出し防止対策をすることがペットの安全にもつながっていきます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。


また地震が起こった際は、まず自分の命を最優先に守りましょう。自分の身の安全を確保し、揺れが収まってからペットの元へ向かいます。ペットの地震対策に関する基本的なことは犬・猫を飼っている場合と共通していますので、こちらの記事も是非ご一読ください。

以上を踏まえて、鳥・魚・爬虫類を飼っている場合それぞれの地震対策をご紹介します。
地震で停電になってしまった時の対策についてはこちらをどうぞ。

鳥の地震対策

まずは鳥の地震対策について。日ごろからできることと、いざ地震が起こった時の行動を見てみましょう。
安全対策
もし地震が来たら、鳥かごは安全でしょうか?何の対策もしていないと地震の揺れによって、こうした被害が予想されます。
- 鳥かごが転倒・転落
- 鳥かごに物がぶつかる
- ガラスが割れて破片が鳥かごに
- 鳥がパニックを起こして鳥かご内の物や壁にぶつかる
地震の際に飼い主がすぐに駆けつけられるとは限りません。自宅に誰もいなくても大丈夫なように、鳥かごの安全対策を実施しましょう。
鳥かごの安全対策では以下のようなことができます。
- 固定した家具の上に鳥かごを置く
- 鳥かごの下に耐震マット・滑り止めシートを敷く
- 鳥かごの周囲に背の高い家具・家電を置かない
- 鳥かご周辺の家具や家電は固定、近くに落ちそうな物を置かない
- 鳥かごを窓ガラス付近に置かない
- ガラスに散乱防止フィルムを貼る
- 窓は常にレースカーテンを閉めておく
- 鳥かご内の物が落下しないように固定する
- 鳥かご内のレイアウトはなるべくシンプルに(パニック時のぶつかり予防)
すぐに実施できることも多いと思いますのでぜひ実践してみてください。
鳥を6羽飼っている方の地震対策です。床に直置きできるのならそれが一番安心ですよね。この方は元々地震対策をされていたのですが、実際の地震で弱いと感じた点を補強されています。
鳥ハムマンション・温室、地震対策タイプ。
ビニールクロスを臭いが取れるまで干し、カーテンクリップで引っ掛けてみた。
あとはお休みカーテンを作らなきゃ。 pic.twitter.com/9iM2I4VMdv— みゅう (@myou_min) November 23, 2016
この方は地震と、停電に備えた対策をされています。
地震時の注意
地震が起こると私たちもびっくりしますが、鳥たちもパニックになることが多いです。鳥がパニックになっている場合は、優しく声をかけて落ち着かせます。
さっき寝ようと思ったら地震きてリビングでオカメパニック…地震もだけどパニックおこしてる時はやく声かけなきゃだから焦る(>_<)こわかったね~😭 pic.twitter.com/cBXb4E5MuN
— PichikoO(飼い主たにり) (@kysg04) May 27, 2017
うおぉ……皆さん、地震大丈夫でしたか?
ウチは愛知県でしたが、いいちこインコさんがオカメパニックを起こして、落ち着くまで、肩に乗せている最中です…😱 pic.twitter.com/Hpbbh7plf6
— いいちこインコの飼い主@花沢りん吉 (@iichiko_hana) March 16, 2022
体に乗せていると安心するという場合も。その子にとって落ち着く方法をとってあげましょう。
中にはびっくりして逃げてしまうというケースも。
大阪府
さっきの地震で窓から逃げました。
地震で家から出ていっちゃいました
メスです。
濃い青色の方です。
まだ飛ぶのが苦手な子なんです。#インコ#インコ迷子 pic.twitter.com/xhzKRBQzBk— 和柄@ショーン (@wagara_yu_gi_oh) June 17, 2018
鳥が逃げ出さないように日ごろから注意しておかなければいけませんね。
避難をするときはどうする?
自宅から避難しなくてはいけなくなったら、原則としては「同行避難」が定められていますが、状況を考慮してペットを連れていくかどうかを判断します。
同行避難とは…
災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し、避難所まで安全に避難すること(東京福祉保健局HPより引用)
ペットを連れて避難する際は、キャリーケースに鳥を入れて避難します。普段からキャリーケースに慣れさせておくとスムーズです。鳥かごに入れて避難する際は、扉が開かないようロックしておきましょう。必要なものは全て持参します。
あっ、そうそう。地震でに備え、鳥籠の近くに緊急避難用の小箱を用意してます。厚紙で作って四方八方に覗き穴をあけてます。小鳥屋さんが販売の時に用意してくれる小箱をやや大きくしたもの。避難する際にバッグにさっと収めて移動できるようにと用意しました。いざという時の為に、愛する彼らの為に。 pic.twitter.com/1zIv3W5AcN
— 映太郎 (@a_taro_1963) August 4, 2019
やむをえず、ペットを置いて避難する際は、鳥かご周囲の危険物を片付けて、エサと水を多めに準備しておきます。余震が起きて隙間が空いた際に逃げ出さないよう、脱走対策もしておきましょう。
魚の地震対策

水がなくては生きていけない魚は、特に地震対策が必要なペットと言えるでしょう。水槽が倒れたり壊れたりしないよう、もし壊れた場合に代わりの環境を与えてあげられるよう準備しましょう。
安全対策
地震の揺れで、次のような被害が起こる可能性があります。
- 水槽が台から落ちる
- 水槽が割れる
- 水槽に物が倒れかかる、ぶつかる
- 水槽内の水がこぼれる、こぼれた水がコンセントにかかる
- 魚が水槽外に投げ出される
- 停電してエアーポンプやヒーターが止まる
こうした事態が起こることを想定し、回避するために日頃から準備をしておきましょう。
- 水槽の固定
- 水槽を置いている台の転倒防止対策
- 水槽に飛散防止フィルムを貼る
- 水槽に蓋をし、固定するコンセントを水槽から離す
- コンセントを保護する…★
- 水槽内のレイアウトを工夫する(重いものは底の内側に)
- 水槽付近の家具の転倒防止対策を実施する
- 水槽の揺れを抑える…★
- フランジ付きの水槽にする…★
★マークの項目については、詳しく説明していきますね。
水槽の地震対策をされている方を見てみましょう。
最近は熱帯魚水槽も水位を下げてるし、金魚水槽はもともと水圧の関係を考慮して低くしてる。
最低限の地震対策。
震度4までなら溢れないだろう❗
たぶん❗ pic.twitter.com/MR3FmdDCxu— なおなり🐣 (@naonari_aqua) March 7, 2021
この方は地震で水があふれ出ないよう水位と水圧を考慮されています。
地震対策もふまえて水槽を接着
連結させている我が家の水槽
隙間に水が入り込み拭くめんどくささや
地震対策も考えバスコークで接着。
ついでに水槽裏に隠していたコンセントもライト上へ。
考えれば考えるほどキリがありませんが見た目も大事にしたいですよね😓#アクアリウム #海水水槽 pic.twitter.com/d6U4GSeAQz— トサ・カラス (@tosakarasu0525) May 29, 2022
この方は水槽を接着して転倒を防止しています。
おはようございます☀
最近和歌山でも震度5弱の地震が発生
という事で水槽棚の地震対策を決行
スチールラックを横に並べて結束バンドで固定し水槽を縦向きに配置しました
あとは下のベニヤ板をダブルにして間に耐震ジェルを挟みます
コレでラックごとぶっ倒れるのは回避出来るかな
あー腰痛て pic.twitter.com/qU9yIrvaMv
— Yama (@Yama_wakayama) March 18, 2021
この方も転倒防止対策をされています。
コンセントを保護する
コンセントに水がかかると漏電したり、片付けの際に感電したりする恐れがあってとても危険です。水槽の水が零れないように対策するのと同時に、コンセントに防水カバーをつけて置くと安心です。
防水機能付きの電源タップもおすすめです。
水槽の揺れを抑える
水槽が大きく揺れると、中の水も揺さぶられてバランスが悪くなり、転倒・落下しやすくなります。水が溢れて魚が外に出てしまう恐れもあるので、揺れを最小限に抑えるのが望ましいです。
免震機能が付いた水槽はまだ販売されていないようなので、耐震マットなどで対策されている方が多いですね。
今日は水槽の耐震?免震?対策をやってみました。(写真4参照)
内容は簡単。
水槽マットと水槽台の間に合板を入れ、その裏に緩衝材をインする、という作業。
(写真2参照)
単に水槽をどかして、板をひく作業なんだけどめっちゃ疲れる😣💦⤵️色々と追加作業が出てくるし…
コケリウム追加しました❤️ pic.twitter.com/TK0EsheejK— っちゃん ⛳ ・ 🏌️♂️ (@BrokenYocchi) June 27, 2020
フランジ付きの水槽にする
フランジとは、水槽の上側開口部に縁取りのように付けるパーツのことです。本来は水圧で水槽の壁が変形しないようにするためのものですが、地震の際はフランジが返しの役割を果たして水が溢れるのを防ぎます。
後からつけるタイプもありますよ。
最近地震多くて怖いね
少し前に水槽の地震対策しましたこのねずみ返しみたいな感じのアクアフランジってやつを三辺に付けてます
これをつけてると揺れが大きくても水がこぼれにくいらしいので、漏電とかを防ぎやすいと思う
本当は四辺つけたほうがいいのかもだけど、酸欠になりそうかなと… pic.twitter.com/ilwy4NOenM— ちる@水野 智絵 (@nemchill_sub) March 20, 2021
一応点検…
水槽のフランジとフタのおかげか、
水槽の水は一滴もこぼれてませんでした本当に揺れがひどいときは、光学センサーに水が触れてポンプが自動停止して水位が下がってくれます pic.twitter.com/cqhH4vGzxu
— mjneko (@mjneko_zeovit) October 7, 2021
地震時の注意
地震が来て揺れが収まったあと、水槽の安全確認をしましょう。その際に漏電や感電を防ぐため、まず電気機器のコンセントを抜きます。
余震が来る可能性もあるため、水がこぼれないように水槽の水を減らしましょう。
関西ではまだまだ余震が続いてますが先日の地震で水槽の水が漏れた方も多いと思います。
水槽を低い位置に置くのは勿論ですが水位を生体に影響無いくらいまで減らしラップを巻いておくとかなり水漏れを防げますよ。 pic.twitter.com/UfbKSUbkDQ
— 大西 慎太郎 (@SHINTARO0024) June 19, 2018
余震に備えて簡易的な蓋を作っておくのもいいですね。
水槽の余震対策に、ラップをガムテープなどでフタ作る方法。ガムテープはがしにくいので養生テープの方が良いかも
コーラルフィッシュvol31より転載 pic.twitter.com/2xlQhlXyFz
— mjneko (@mjneko_zeovit) March 16, 2022
地震の際の水槽への対処について、こちらのサイトで詳しく解説しています。参考にしてください。
やむを得ず魚を置いて避難する際は、水槽の周りに倒れかかったりするような危険物がない状態にしておきます。
爬虫類の地震対策

爬虫類といっても小型のカメやトカゲから大型のヘビやワニまで、種類は様々です。それぞれの種類で必要な物やお世話の仕方は異なりますので、ここでは基本的な共通項目についてご紹介します。
安全対策
地震が起こると以下のようなことが起こる可能性があります。
- ケージが落下する
- ケージが壊れる
- ペットが脱走する
- ケージに物が飛んでくる
室内の地震対策でできることは以下の通り。
- ケージを固定する
- ケージの周囲に危険物を置かない
- ドアや窓から逃げ出さないように対策する
大型の爬虫類や危険種を飼育している場合は、脱走対策を特に厳重に行いましょう。
実際に地震対策をされている方を見てみましょう。
【爬虫類の地震対策の提案🐍】
1、ホムセでL字、当て金、ネジ、ゴム板等をそろえます。ゲージ一つ分なら500円前後です。2、L字の内側にゴムをつけます。
3、図の要領でマルチラックなどに固定します。
4、写真のように何個かつければ、ゲージが飛び出ることはないと思います。 pic.twitter.com/ZZIceCjUYX
— シルバーBack (@CBreprep) June 18, 2018
こちらは200匹の爬虫類を飼っている方の動画。地震対策について解説されています。 同じ方の動画で実際に震度4の地震があった後の状況を説明されています。私の住んでる所は今回揺れて無いんですが、ほぼメタルラック管理の私はこんな地震対策してます。
ケージが落ちない様に100均の自転車コーナーにあるゴムロープを張る、往復回数でテンションも調節出来ます。
揺れ防止にメタルラックや棚用の天井利用した固定具。
後は普通に突っ張り棒とかで揺れ軽減。 pic.twitter.com/nUL8doqvKU— トギ (@pso_togi) February 13, 2021
地震時の注意
地震が起こったら以下の通り理に対応しましょう。
エサを中止する
地震が起きたら、エサを与えるのをストップします。エサを与えるとストレスによる吐き戻しをすることもあるので、水だけ与えるようにしましょう。種類にもよりますがエサを食べなくても、数日〜数週間は生きられます。
環境が整ったら再開しましょう。
活動性を下げる
また温度を徐々に下げて、活動性を下げます。こうすることで体力の消耗と脱走を防ぐことができます。
どのくらいまで温度を下げるのが適切かは種類によって違うので、普段から温度管理はしっかりしておきましょう。
避難する時はどうする?
ペットは同行避難が原則となっていますが、爬虫類の場合は避難所に連れて行くのが難しい場合もあります。特に、毒性があったり、大型の場合は連れていけないと思っておきましょう。
実際に爬虫類を飼っている人の避難アイディアも参考にしてみてください。
ペットを置いて避難する場合は周囲から危険なものを排除し、水分が摂れるようにしておきます。余震で隙間が空いて逃げる可能性もあるので、脱走対策は厳重に行ってください。季節によっては暑さ・寒さ対策もして、可能な限り様子を見に来るようにしましょう。
ペット用の防災グッズを用意しよう!

自分たちの防災グッズはもちろん、ペット用の防災グッズを用意しておきましょう。
鳥類、魚類、爬虫類などは避難所に連れていくことが難しいかもしれませんが、準備をしておけば知り合いに預けたり、ペットホテルに預けるとなった時に安心です。いざという時に預けられる場所を日ごろから把握しておくことも重要ですね。
用意しておくものは以下の通り。
- エサや水
- 食器
- 薬(普段から服用している場合)
- おもちゃや毛布などあると安心するもの
- 中に入るケージやバッグ
など。基本的に普段使っているものを多めにストックしておけば大丈夫です。
また、ペットとはぐれてしまう場合や病院に連れていく場合もありますのでペットの情報(名前・種類・外見の特徴・年齢・性別・既往歴・かかりつけの動物病院など)をまとめてペットに身に着けさせる、もしくは近くに置いておくとよいでしょう。
飼い主側はペットと一緒に写っている写真があると捜索や、受け取りの時に役立ちます。
ペットだけでなく自分たちの防災グッズもしっかり用意しておきましょう。

まとめ
災害時は自分の命や生活を維持するのも大変ですが、ペットを飼っている以上はその命を守ることも必要となります。いざというときの負担を少しでも減らせるよう、普段から準備をしておきましょう。
地震で停電してしまうと命に関わるペットたちも。ペットの停電対策はこちら。